生活再建さまざまな支援制度
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。
自然災害で被災した際に、生活再建への取り組みを行うさまざまな支援制度が用意されています。支援制度の種類や申請について確認しましょう。

一定規模の自然災害で亡くなった方の遺族に対して、弔慰金が支給される制度です。亡くなった方が世帯の生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円が支給されます。

| 受給できる遺族 |
|
|---|
一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。

| 対象となる障害 |
|
|---|
一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた方に対し、生活再建のための支援金が支給される制度です。住宅の被害程度や再建方法によって、最大で300万円が支給されます。
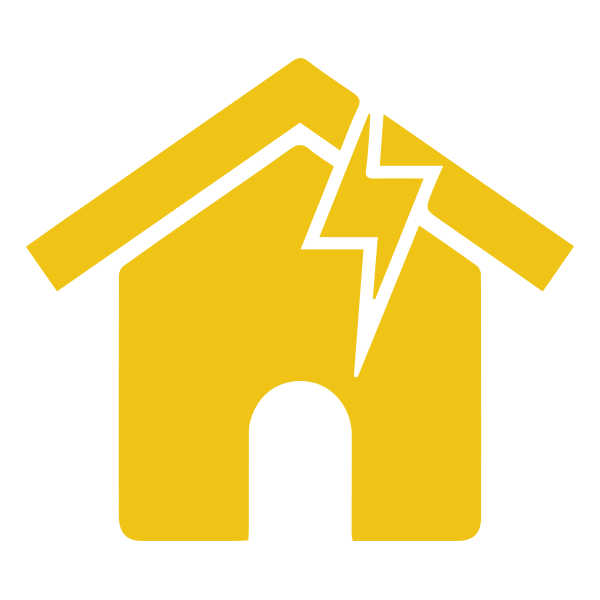
| 対象となる人 | 一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯 |
|---|
一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。

| 対象となる人 | 一定規模の自然災害で負傷された方、または住居や家財に損害を受けた方 |
|---|
所得の少ない世帯などが、緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的として少額の貸付を行う制度です。
| 貸付の対象となる理由 |
|
|---|
生活福祉資金の特例貸付
(緊急小口資金)(Yahoo!くらし)
自然災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合、所得税の軽減や免除を受けられます。
納税者は次の2つの制度から、より有利な方法を選択して確定申告の際に適用できます。
雑損控除とは、自然災害によって資産に損害を受けた場合などに受けられる所得控除です。

| 雑損控除の対象になる資産の要件 | 損害を受けた資産が次の両方に当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること
(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること※ 事業用の資産や、別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個または1組で30万円を超えるものなどは当てはまりません。 |
|---|
出典:国税庁ホームページ
災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減または免除されます。
災害によって受けた住宅や家財の損害金額がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方
| 所得が500万円以下の場合 | 所得税の額の全額 |
|---|---|
| 所得が500万円を超え750万円以下の場合 | 所得税の額の2分の1 |
| 所得が750万円を超え1,000万円以下の場合 | 所得税の額の4分の1 |
出典:国税庁ホームページ
住宅復旧のための建設資金または購入資金に対する融資です。

| 実施機関 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
|---|---|
| 利用できる人 | 災害で住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「罹災証明書」を交付されている方が利用できます。
※既に被災住宅の復旧が行われている場合は、原則として融資をご利用いただけません。 |
2024年06月20日公開